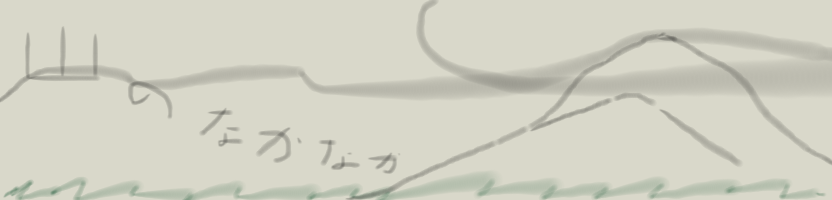リニューアル工事中
Jackサウンドサーバー
導入前に標準のカード番号設定をして、GUIの音が出るよう基本的な設定が終わっている状態になっていたほうがいいです。オートプラグ設定のカードなど、インストール後挿し直すとほぼ自動で種類を判断して設定がされます。(詳しい方はALSAの設定を書き換えることで強制的に設定も可能)標準の2スピーカーアンプ付きを1本差しなら問題なく音が出ると思われます。
公式のHPにある、追加リポジトリを導入(ソフトの取得でファイル名をいれ1クリックインストールをすると、リポジトリの登録も同時にできてしまう、後で更新の設定などをしないと増えすぎて更新に時間がかかりすぎる場合あり)
(obs オープンビルドサービスのリポから)
Cadence
Calf (エフェクターのセット、音源やリミッターで見た目も音もいい感じ)
alsa-plugins-jack(多数のリポジトリが有効の場合、依存関係で問題が出ます、oss,non-ossのリポだけ有効にするなど対策を)
pulseaudio-module-jack
RTカーネルがなかったのでカーネルソースからビルドしなおしてみました。
make menuconfigで割り込みを300Hzから1000Hzに書き換え1時間以上かかってビルド、書き換え前のカーネルもリアルタイム設定になっているので、バッファーを1024ぐらいまで大きくすれば音が途切れず聞けますが、レイテンシーが20ms以上
ビルドし直したカーネルは512,2で6msあたりで安定して聞けました、さらに小さくして3msにするとプチプチでした。
利用しているデスクトップによって多少設定が異なります。
PulseAudioが標準のサウンドサーバーとなっていますが、バックエンドにPhonon GStreamer が使われています、GStreamer-0_10-plugin-good などがJuckとの接続に使われてるらしい(別途入れた覚えはありません)、Juck導入時ボリュームコントロールがクラシュしてしまい停止(再起動後動くように)
普及の方法が不明、Gnomeをメインに使うので詳しく調べてません。
音量が小さい場合、YaSTのサウンド設定の、その他のメニュー内にある音量調整で調整(メイン100%、マイク系は使わなければ0%、スピーカー系100%)
次にデスクトップのボリュームコントロール
それぞれのデスクトップ設定のサウンド関係設定ツール
通常ここまでで正常に音量が上がると思われます。
追加で更にあげたい場合Pavucontrol (インスト後表示名、Pulse Audio 音量調節)を入れて、さらに150%(50%ブースト、150%にしたあと通常のデスクトップ系のボリュームが動くと100%以下にまた戻ってしまいます。
実用的には100%で使い、小さい音の底上げはリミッターやコンプ等を使うのもいいかも、ネット動画は音量がまちまちで面倒なのでリミッターを入れて見ています、リバーブをかけ声を聴きやすくしたり、サチュレイタで耳障りなサシスセソを下げるなんてことも。
ここまででJackが使える状態となると思います、起動できない場合、PCの再起動、プラグの挿し直し、YaSTのサウンドカード設定と音量、Pulseaudio-module-jackが入っているか、入れたあと再起動したか、各デスクトップのサウンド設定で、Jack sinkが接続先になっているか、JackSinkINからHardwarePlaybackに結線されているかなどを確認してみてください。
Flashの旧版(Firefoxなど)はJack起動中音が出ません、PepperFlash系HTML5系は出ます。
Pulseaudioからコントロール系を奪う方法として、下に書いたものがありますが問題もあり、Wineの32Bitなどの音がPulsaudio-alsaを利用しているため出なくなるとのことです。
他にも問題が出ないとはいえないため注意してください。
(Mplayerの音もPulseaudio-alsaを使ってるかもしれません)
etc/pulse/この中の default.pa を
#load-module module-udev-detect
#load-module module-detectbr
とコメントアウト
load-module module-alsa-sink device=dmix
load-module module-alsa-source device=dsnoop
を追加で書き込む
<
くわしくはAlsaaudioのWikiなどでお調べください、意味不明の場合、触らないこと。
pulseaudio-alsa を削除してALSAにアクセスできなくするとのことですが、問題が多すぎ結局残したままで使ってます。
Pulseオートスポーンの停止(私はこの設定をしていません、JACKを使わない時でも起動させなければならず手間がかかる)
Cadenceを使う場合停止起動をクリックするだけでできる、ツール類を起動するとPulseを停止するようになっているため、下の設定をしなくてもJackを使えるみたいなので、私はオートスポーン停止をしていません。
/etc/pulse/client.conf の
; autospawn = yes
; daemon-binary = /usr/bin/pulseaudio
この部分を
autospawn = no
daemon-binary = /usr/true
に書き換える
Cadense を使う場合Pulseのスタート、ストップをGUIでできますが、使わない場合
ps ax | grep pulse このコマンドで現在のPulseの状態確認をみられます。
pulseaudio --start (動かします)
pulseaudio --kill (停止します)
で動かしたり、止めたりします。
Pulseはマウスクリックの音やらフォルダーの開閉音さまざまな音が出る瞬間にリスポーンするため、上の方法で書きかえてリスポーンをとめてしまったほうが起動しやすいと思います。
くれぐれも、自己責任でやってください、個人的な覚書程度です。
Blender
Blender本体とBlender-langが必要(Leap42.1のOSSリポ)
日本語設定
起動後左上メニュウからFile→User Preferences→Systemタブの International Fonts をチェック(落ちる場合Blender-langがインストール済みか確認)
文字化けする場合、ホルダーアイコンを押してusr/share/fonts/truetype/
ipaexg.ttf
など、日本語対応のフォントを設定
Transleteのボタンを押して(3種類)各部に反映
ユーザー設定の保存を押す
マウスボタンの左右入れ替えが、入力のタブ内にあるのでお好みにより切り替える、私は逆さまが耐えられず切り替えて使用してます。
標準になく外部から落とした.ttfファイル入れたい場合ファイルをクリックすると専用インストーラーが起動してくれると思います。
GV-MVP/RX(TVキャップチャーカード)
TVチューナーカードでMPEGエンコーダと旧アナログTVと古いカードですが、コンポジットとS端子がついており使っています。ドライバーは
ivtv
ivtv-firmware
ivtv-utils
v4l-conf
v4l-tools
インストール後
sudo modprode ivtv
このコマンドでivtvのドライバーを有効化、/dev/video0とゆうデバイスシンボルがあれば成功(ivtv-firmwareがないとシェルからコントロールできなそう)
このシンボルを右クリックして、アプリケーションで開く
VLC、Mplayer、などMPEG2が再生できるソフトを選べば見れました
入力するピンがSビデオかコンポジットに切り替えがあり
v4l2-ctl -d /dev/video0 -i 2 -s 2
このコマンドを実行すると、コンポジット
v4l2-ctl -d /dev/video0 -i 1 -s 2
1にするとS端子
0 でチューナになりますがもう使うことはない
細かい設定を触る場合
pv4l2
デバイスにvideo0を選ぶと、音量やエンコード、すべての項目がグラフィカルな環境でいじれます
#!/bin/bash
v4l2-ctl -d /dev/video0 -i 2 -s 2
aplay --buffer-time=0 -f dat < /dev/video24 &
mplayer -framedrop -nocache /dev/video32 -demuxer rawvideo -rawvideo
ntsc:hm12:fps=59.94 -vf dsize=600:-3 -vo x11 && killall aplay
これをメモ帳などで作り、TVとか好きな名前をつけ(シェルスクリプト)実行可能とし、usr/local/bin/などにほおりこめば、ファイル名をコンソールで実行も可能になります。(Mplayerがインストされている前提)
グラボのドライバーがノーマルの場合CPU(E7200)負荷80%あたりでした、GT740のメーカードライバーだとハードウエアエンコーダーが使えるため、CPU20%、GPUはほぼアイドル10%程度、動画のサイズが800*600ぐらいなので、作業しながら裏でTV(地デジチューナーからビデオコンポジット接続)などもできそうです。
スクリプトはx11(xv など対応した物に)となっており、グラボのドライバーを入れてあったりするときは、Mplayerの設定を変える必要があります。
-vo vdpau
としてグラボの機能を使った設定にするとCPU10%、GPU5%ハードのエンコのみになるので見ていてもほぼアイドル状態まで下がりました。(窓は5枚ぐらいひらいてこのページを書いている状態)
ビデオプレイヤー
MplayerQMplay2
mpv
SMplay
Mplayerベースの物はたくさんの派生フロントエンドがあるみたいです、mpv(SMplay入れるとついてくる)はシンプルでファイルの方から呼び出す時などにいい感じ、QMplayは本体を立ち上げて使う感じで、Youtubeの動画検索など機能豊富見た目は地味な感じ、SMplayerは追加でYoutubeのプラグインなどがあり綺麗な見た目でした、Youtubeの検索に候補が出ないなどちょっと使いにくい部分も多少ありますが、VDPAUで動かすとYutubeがCPU負荷10%ぐらいで見られブラウザの意外に高い40%近い負荷(普段CPU負荷などあまり気にしていなかったので結構高いなーと実感)から考えると作業中のバックで聞きながらとかもできそうです。
VLC
何でもありの多機能が魅力、定番なので使ってる方も多そう。
コーデックの関係で追加リポジトリーの物でないと使えませんが動作も安定、日本語にするためのランゲージパックを入れれば大丈夫そうです、導入時にランゲージが自動で入る場合と、別途入れなければいけない時がありました、Langの付いたファイルを導入時に入れとくといいかも。
Unity3D
ゲームエンジンのUnity3DLinuxで動作可能なバージョンがありインストールの予定(HDD問題で現在保留)
ホームに戻る