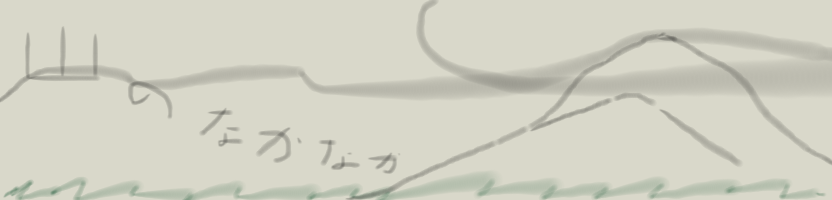リニューアル工事中
Jackサウンドサーバー
Qjackctl(バージョン1、バージョン2(今回は2)、QtでプログラムされてるのでQなのかな)
Pulseaudio-module-jack (Pulseaudioと同居するとき必要、Mintの標準がPulseaudioのため)
この2このソフトをインストール→Qjackctlを起動→設定(U)→パラメーターでサンプルレート(CDが44100)フレーム(F)でバッファーのサイズ、ピリオド(B)でいくつバッファの数を変えられます、サイズが小さいほうがレイテンシーが下がりますが、音がプチプチ切れてしまうため調整
設定はRTカーネルでない場合、リアルタイムのチェックを外し512,2さらにプチプチ切れる場合1024,2とおおきくしていく必要あり
RTカーネルの場合リアルタイムのチェックを入れて250,3など小さめでも動作できる可能性があります。
オプション→スタートアップ時にスクリプト実行をチェック→ pacmd load-module module-jack-source channels=2; pacmd load-module module-jack-sink channels=2; とスクリプトを設定→
OKを押して設定を確定して閉じる→開始(S) 起動エラーが出なければ成功 pulseaudio --kill (停止コマンド)
pulseaudio --start (スタートコマンド)
Pulseaudioがクラッシュしてなければコマンドが実行できると思います(PCを再起動すれば動きます)
止めるとフラッシュなどの音が出せなくなるため、連携のほうがいいと思いますが。
Pulseaudioはクラッシュしてなければすぐに再起動してきます、再起動を止めるには
/etc/pulse/client.conf このファイルを
autospawn = yes
daemon-binary = /etc/pulse/client.conf
この部分を下のように書き換える
autospawn = no
daemon-binary = /bin/true
スタートにスクリプトを設定する前に動かした場合Pulseaudioがクラッシュして動いてない可能性が、)
設定内のAdvancedで細かい設定があるのですが、いじる場合Pulseaudioを完全停止にしないと競合します、止める方法もありますがPulseaudioでしか音が出ないソフト(フラッシュなど)などもあるため止めない方がいいかも。
Mintのタスクバーにあるボリュームコントロールから設定を開いてJackに音を送るため入力のソフトの接続を設定変える必要あり、ソフトごとに一度設定するとPulseが記憶します。
起動させる順番はボリュームコントロールの出力側設定をして→QJackCtl起動とスタート
音関連ソフト(ブラウザやプレイヤー)を起動、音が再生されてる状態でボリュームコントロールの設定→入力(再生中のソフト)の接続先をJackシンクに切り替え、Qjackの接続で結線、1回設定すると次回は記憶していて自動的にシンクになる、競合するとPCの再起動しないと音が出ない可能性あり
KXstudioのソフトを使う場合
(同名のLinuxディストリビューションがあります。インストールするとJackなどが最初から使えます)Ubuntuのリポジトリを追加
sudo apt-get install apt-transport-https software-properties-common wget
wget https://launchpad.net/~kxstudio-debian/+archive/kxstudio/+files/kxstudio-repos_9.2.2~kxstudio1_all.deb
sudo dpkg -i kxstudio-repos_9.2.2~kxstudio1_all.deb
Cadenceを起動→Configureでサウンドカード、IN、OUT、バッファーなどを設定→Start
このソフトのいいところは、Pulseaudioの停止起動もできたりします。(Puiseaudio-module-jackをインストールしてある必要あり)
ツールタブからClaudiaを起動→Studioタブ→SAVEで現在の接続を保存しておけます。
リポジトリを追加した場合Mintのメニュー→システム→ソフトウエアの管理でソフトのインストール削除ができます。(アップデートなどもサポート)
同様にSynapticパッケージマネージャでもできます。
サポートツールなど一式インストールしてみました、単独でサイトから落とした場合何かがたりず起動できなかったのでリポ入れてしまったほうがよさそう。
細かい使い方は、書くのが非常に多くきびしい、CadenceのTweaksタブでDssi、VSTなどのプラグインのホルダーの指定読み込み、Wineasioのチャンネル数とかも設定できます。(Wineasioがインストールされている場合)
CladiaはLadishのフロントエンドとして動くので、このソフトが起動しない場合、Ladishがインストールされているか確認、なければ入れてください、再三入れなおしなどしてまして、たぶん別々に入れたと思います。
不満といえば名前が似ていてわかりづらすぎる
エフェクター
ボコーダやサチュレータ、オルガン音源などもついている、結線もできますがClaudiaから起動してビジュアル的につなぎ、結線状態の保存をしたほうがいいと思われます。
Wineasio
sudo adduser $(whoami) audio
sudo adduser $(whoami) disk
Winetricksを起動し、Select the default wineprefix (デフォでここになってる) OK で進み Change settings
にチェックを入れ OK sound=alsa をチェックしてWineのサウンド出力をALSAにする、OK を押し反映させたら、Winetricksを閉じる
Qjackctlが必要になります
Wineasioのdebパッケージをインストール(KXstudioのレポジトリ登録後 sudo apt-get install wineasio )
libjack-jackd2-0
jackd2
Qjackctl
が入っている状態に、他で色々入れていたのですでに入った状態になってましたが、別途入れたか不明
usr/lib/i386-linux-gnu/wine/
usr/lib/x86_64-linux-gnu/wine/
どちらかのフォルダー内にある wineasio.dll.so を探しコピー、これを .wine/drive_c/windows/system32/
の中にペースト wineasio.dll.so のお尻の .so をリネームで取り wineasio.dll にする
Wineで繋ぎたいDAW(asioのオーディオ入出力があるソフト)などを起動 起動するだけで特にいじらず
regsvr32 wineasio.dll
を端末で実行(64Bitの場合 wine64 regsvr32 wineasio.dll )
WineのレジストリーにWineasioが登録される
私の場合このままでは音が出ず、Cadence を起動(JackはStopのまま) Tweaksタブを開き WineASIO
この中の Connect to hardware Autostartserver Fixedbuffersize この3個にチェックがついた状態(Autostartserverをチェックした)にかえ、ApplyNowで変更を確定
DAWを起動してASIOの設定にする、これでつながりました。 読めない英語と格闘しつつ多数の情報を元にためしたため正確ではない部分があります。
REPER
フリーで最新バージョンもお試し可能となっているようで、特に制限もなくスタート時有料登録のポップがしばらく出る、カウントダウン後、フリー版として使える上のWineASIOを利用
Win版をDLしてWineにインストール
日本語のパッチをDL
Japanese.ReaperLangPack
.wine/drive_c/users/名前/Application Data/REAPER/LangPack/
にファイルを入れる(Japanese.ReaperLangPack)
Blender
最新を入れたい場合、直DL→解凍(ホルダーをHOMEなどに作りその中に)→解凍したフォルダー内のBlenderをクリックして起動、クリックしても起動しない場合プロパティーを開き起動にチェックが入っているか確認
Mint Xfceの場合デスクトップで右クリックしてランチャーを作れる、更新されないので自分で最新版を確認する手間がかかる
最新版は2.76b(2016/03) 日本語化
起動後左上メニュウからFile→User Preferences→Systemタブの International Fonts をチェック
文字化けする場合、ホルダーアイコンを押してusr/share/fonts/truetype/
takao-gothic/TakaoExGothic.ttf
noto/NotoSans-Regular.ttf
など、日本語対応のフォントを設定
Transleteのボタンを押して(3種類)各部に反映
ユーザー設定の保存を押す
マウスボタンの左右入れ替えが、入力のタブ内にあるのでお好みにより切り替える、私は逆さまが耐えられず切り替えて使用してます。
Unity3D
Mint17.2で使っていたのですが、17.3でグラボドライバーがうまく動かず保留中
Wineで動かす旧方式ではなく、Linux版が公式試験ビルドとして公開されてます。
ホームに戻る